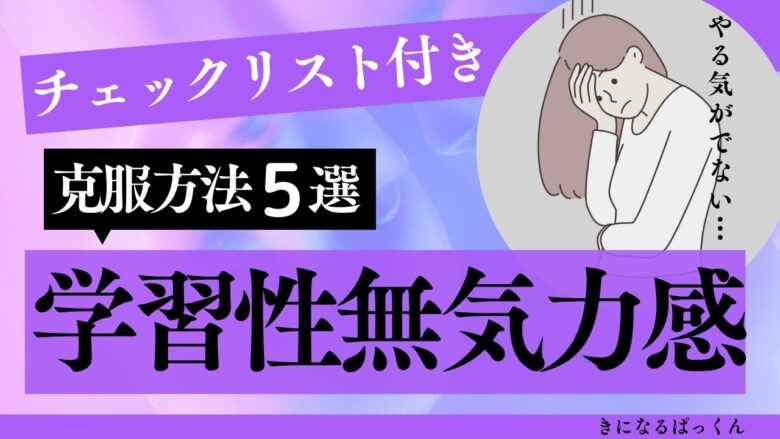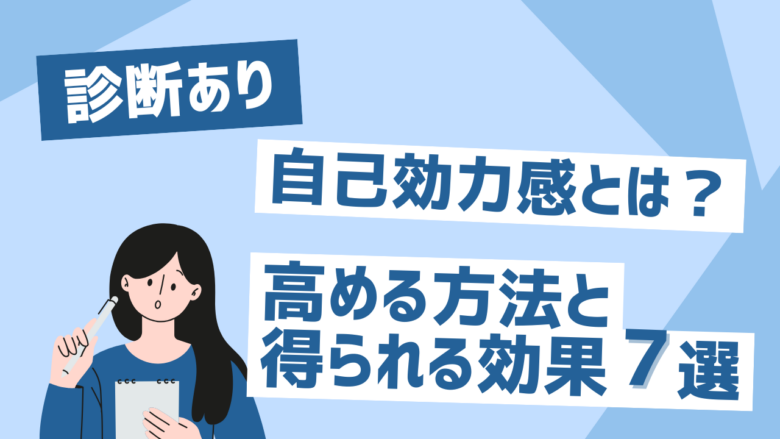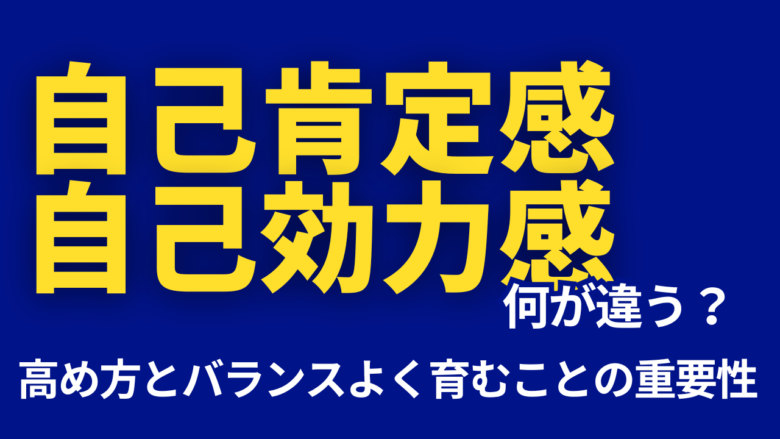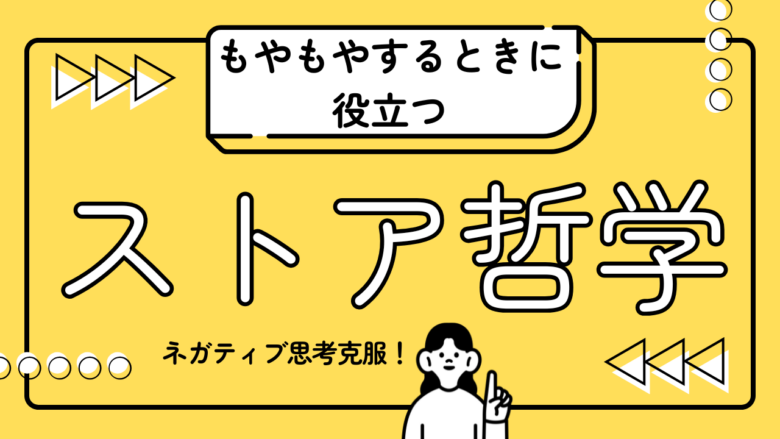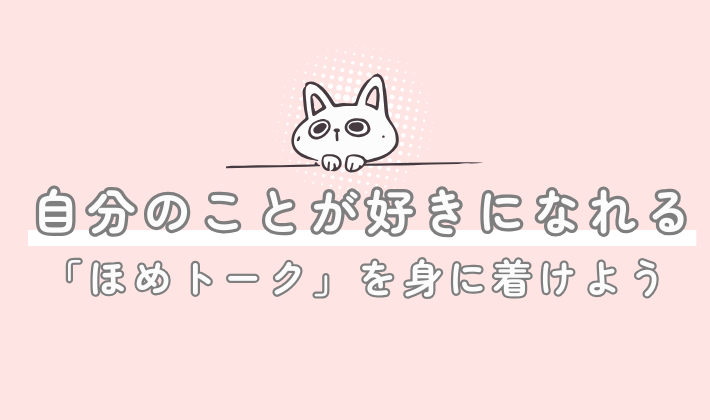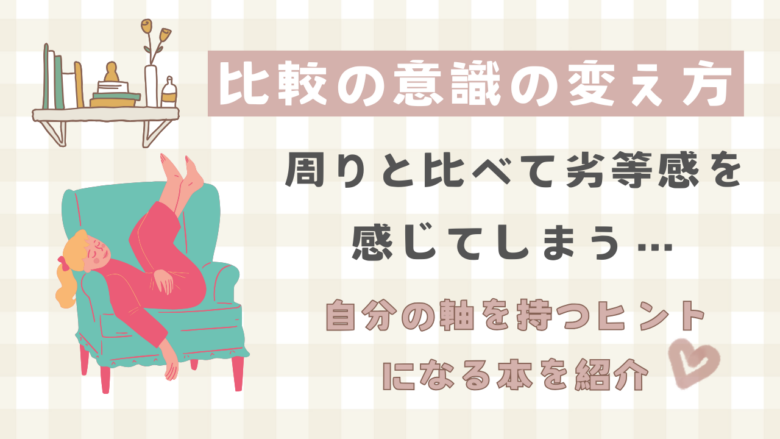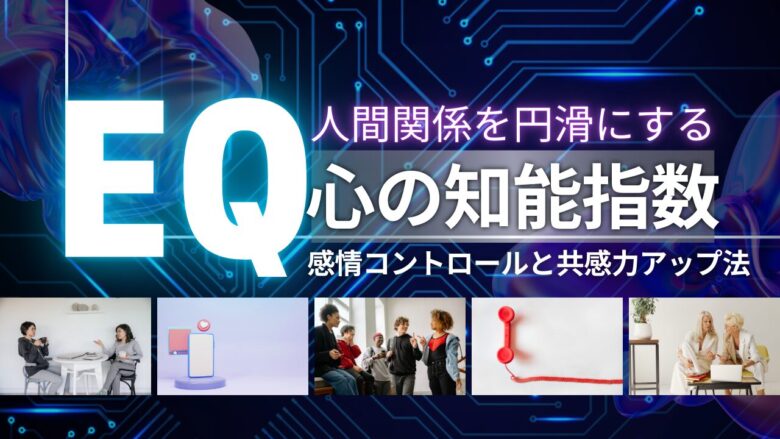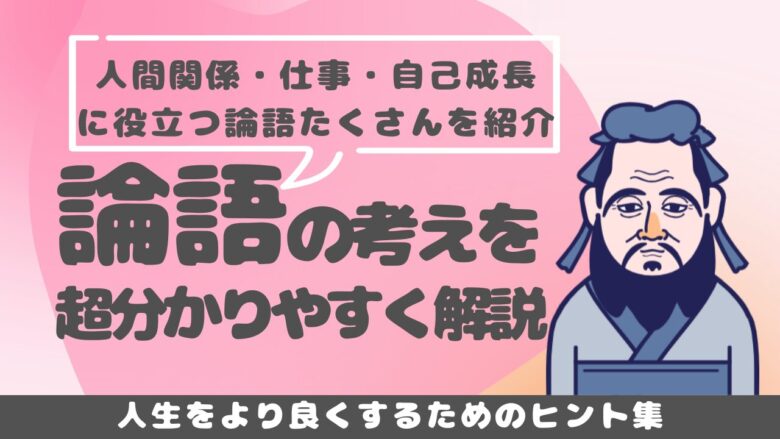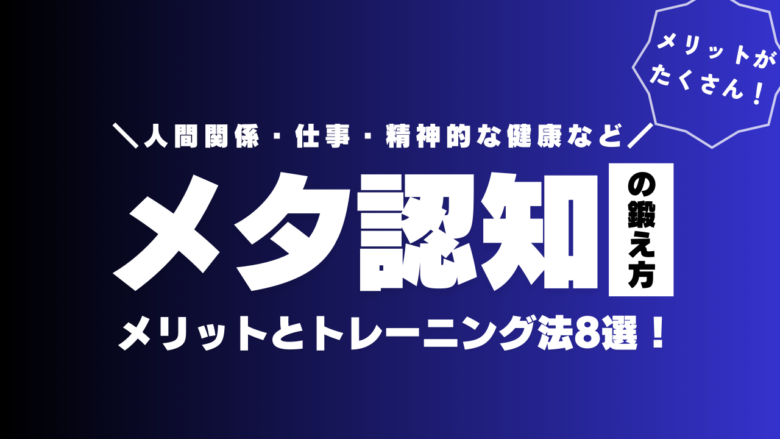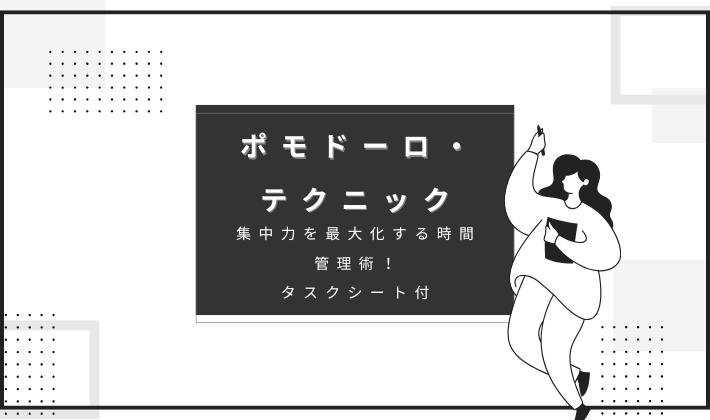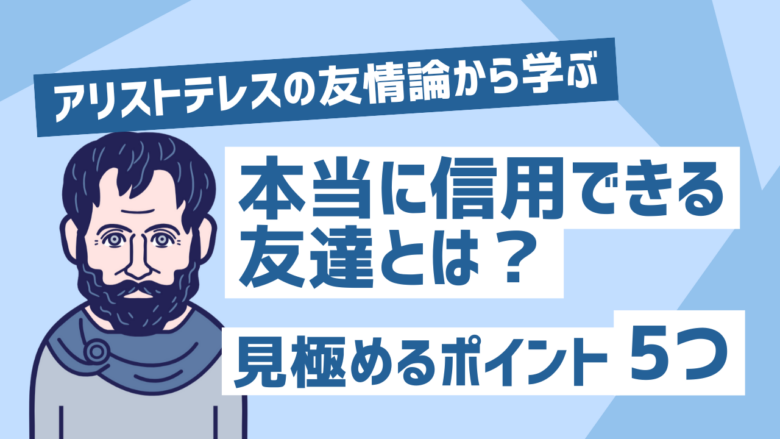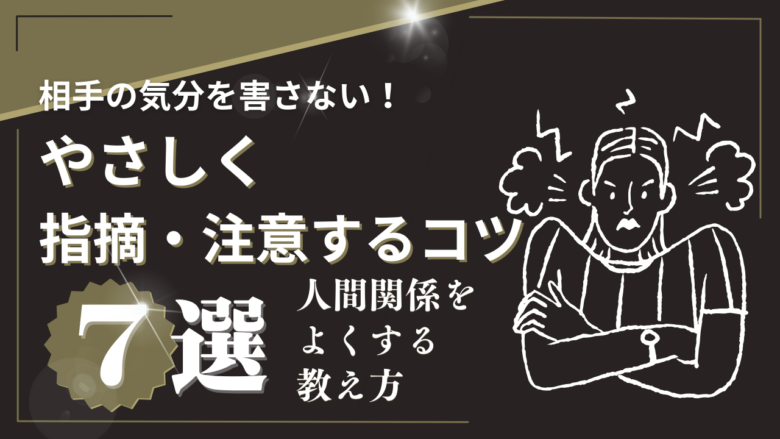「頑張りたいのに、やる気がでない」と感じたことはありませんか?頭では「やらなきゃ」と思っていても、体が動かない。何か始める前から「どうせうまくいかない」「やっても意味がない」と感じてしまう。もしかしたらそれは、「学習性無力感」と呼ばれる状態かもしれません。それは心が、自分を守ろうとしているサインなのです。

miho
この記事は次のような人におすすめです!
- 自分を責めてばかりいる
- 何かを始めても、「どうせ続かない」と思ってしまう
- 最近、何をするにもやる気がでない
- 「頑張りたいのに動けない」と感じることがある
- 生きるペースを取り戻したいと思っている
職場や学校、友達関係など、社会の中で生きている限り、人との関わりは避けられません。だからこそ、多くの人が、大なり小なり人間関係の悩みを抱えているのではないでしょうか。
国内で300万部を超えるベストセラー『嫌われる勇気』では、アドラー心理学の考え方として「すべての悩みは対人関係の悩みである」という主張が紹介されています。
このサイトでは、そんな人間関係の悩みを解決するためのヒントをまとめています。
この情報が、あなたの人生を少しでも生きやすくする手助けになれば嬉しいです!
学習性無力感とは?

「何をしても無駄だ」と学習してしまう心のクセ
学習性無力感(がくしゅうせいむりょくかん)とは、何度も「努力してもうまくいかない」という経験をするうちに、心が「頑張ってもムダ」と思い込んでしまう状態のことです。つまり、
- 努力しても、結果が出ない
- がんばっても、状況が変わらない
この状態が続くと、もうやっても意味がないと感じるようになります。
犬の実験からわかったこと
この考え方は、心理学者マーティン・セリグマンが1960年代に行った犬の実験から発見されました。
- 犬をハーネスで固定し、電気ショックを与える
- 最初のグループはどんなに頑張っても逃げられない状況
- 別のグループはボタンを押せば止められる状況
→そのあと、どちらのグループにも「簡単に逃げられる場所」を用意したが…
逃げる方法を知っていた犬は脱出したが、最初に逃げられなかった犬は何もしなかった。

無力を学んでしまった犬は、逃げられるのに何もしなくなってしまったのです。
「無力感の学習」は人間にも起こる
この現象は、犬だけの話ではありません。
人間も、似たような経験をすると、同じように無力感を感じます。たとえば、
- 何度も試験に落ちた
→「どうせ勉強してもムダ」 - 意見を言っても毎回否定された
→「何を言っても聞いてもらえない」 - 頑張っても認められなかった
→「自分には価値がない」
こうした否定される経験の積み重ねが、やる気の消失や行動しないというかたちで表れていきます。
日常で生まれる「学習性無力感」の具体例
なんで私だけ、こんなにうまくいかないんだろう
SNSではみんなキラキラして見える。
結婚した、子どもができた、豪華な買い物をした、仕事で評価されたとか、みんなうまくいっているみたい。
自分だって努力しているのに、全然結果が出ない。むしろ失敗続きで、笑われてる気がする。

どうせ私なんか、あの人たちみたいにはなれない…
言ってもムダだから、もう黙ることにした
職場で何度も改善案を出してきたけど、帰ってくるのは決まって「うちはそういうやり方してないから」「新人が口出すことじゃない」などの冷たい意見ばかり。
最初は勇気を出して言っていたけど、何度も冷たくされてもう何も言えなくなった。

意見なんて言わなければよかった…自分が間違ってたんだ
なにかを始める前から、心が諦めている
朝起きて、「今日はちょっとだけ片づけよう」と思う。でも、気づいたら何も手を付けないまま夕方にまっている。「やろう」と思ったのに動けなかった自分を責めて、ますます動けなくなる。

やる気が出ないんじゃなくて、どうせ無理って、心が勝手にブレーキをかけてる気がする…
心の中の「あきらめグセ」チェックリスト
あきらめグセチェックリスト
20の質問に「はい」か「いいえ」で答えてみましょう。
学習性無力感が生まれる原因
学習性無気力感は、ある日突然現れるものではありません。
小さな失敗や否定、努力が報われなかった経験の積み重ねが、じわじわと心を追い詰めていきます。
1.頑張っても結果が出ない経験が続いたから
- 勉強をしても点が上がらない
- 何度受けても面接に落ちる
- 毎日ジムに通っても体重が変わらない
こうした「努力→失敗」の繰り返しは「やっぱり私には無理なんだ」というあきらめを心に刻みます。
本当は、やり方を少し変えればうまくいくかもしれません。でも、心はすでに「むだだよ」とブレーキをかけてしまうのです。
2.否定される・認めてもらえない環境にいたから
- 頑張って提出したレポートをひどく評価された
- 職場での自分の提案を一蹴され、別の人がいったら採用される
- 親や先生に褒められた記憶がない
こうした努力を認めてもらえない体験は、「私は認められる存在じゃない」というセルフイメージを作り、やる気を奪っていきます。否定は、心のエネルギーを静かに削ります。
3.コントロールできない状況に長くいたから
- 理不尽な上司の機嫌で評価が左右される
- 家庭の事情で自分の進路を自由に決められない
- 大人の顔色ばかり気にして育った
このような自分では変えられない状況が続くと、「どうせ何をやっても意味ない」とい思考のクセが身についてしまいます。
学習性無力感の根底には、心が傷つきたくなくて身に着けた防衛本能があります。
何度もがっかりしないように、何度も否定されないように、「最初からやらない」ことで自分を守っているのです。
つまり、あきらめは怠けではなく、生き残るための選択だったのかもしれません。
学習性無力感の克服法5選

1.小さな成功体験を積む
「できた」という感覚が心のリハビリになります。
「やる気がない」と思っているときでも、実は行動する気力がゼロなわけではありません。
ただ、いきなり大きな目標を立てると、余計に動けなくなるのです。たとえば
- とりあえず机の上を1分だけ片づけてみた
- 10分だけ散歩に出てみた
- アプリを開いただけでもOK
このようなハードルの低い行動を自分で認めることが自己効力感(自分にもできるという感覚)を少しづつ育ててくれます。大切なのは、「やったこと」より「やれた自分」をちゃんと見てあげることです。
2.自分にコントロールできる部分だけに集中する
変えられるのは、他人でも結果でもなく、今の自分の選択です。
無力感を感じるとき、人はどうしようもないものにばかり意識が向きがちです。
- 他人の評価
- 過去の失敗
- 未来への不安
でも本当に変えられるのは、今、自分が何を選ぶかだけです。たとえば
- 朝、10分早く起きる
- 話す相手を変えてみる
- SNSのアカウントを整理する
小さな選択の積み重ねが、「自分にはコントロールできることがある」という感覚を呼び戻してくれます。
3.自分への言葉遣いを変える
「ダメだな」より、「疲れてるんだな」で救われることもあります。
やる気が出ない時、自分にこんなふうに言っていないでしょうか
- なんで動けないんだよ…
- またサボってる…
- 怠けてばっかりで情けない…
でも、もし友達が置ない状況だったら、どう声をかけますか?
きっと、「よく頑張ってきたじゃん」「そりゃ疲れるときだってあるよ」と言ってあげたくなるはずです。
同じように、自分にも「優しいひとこと」をかけてあげましょう。心は、自分の言葉にいちばん影響を受けているのです。
4.他人と比べない、自分だけのものさしを持つ
成長は、横ではなく縦にみましょう。
誰かに比べると、たいてい落ち込みます。あの人の方が早い、うまい、楽しそう…
しかし、自分のペースや背景は全く違うはずです。だから、比較するなら昨日の自分、1週間前の自分にしましょう。
- 前より早く起きられた
- 落ち込む時間が短くなった
成長はミリ単位でい進むものです。気づけたとき、自信に変わります。
5.環境を少しだけ変える
やる気は内側だけじゃなく、外側からも引き出せます。
人間は環境に影響される生き物です。意志の力で立ち直るのが難しい時は、場所や道具、人間関係などの外の要素を見直すのもとても有効です。たとえば
- いつもと違うカフェで作業してみる
- 明るい照明や香りで、部屋の空気を換える
- 話していて前向きになれる人と関わる時間を増やす
「何かを変える」のは、あなたの中じゃなくて周りからでもOKです。
学習性無力感は、心が静かに疲れてしまった証拠です。無理に引っ張り出すのではなく、小さな「できた」を積み重ねることで、自分を取り戻すことができます。

やる気は、どこかから湧いてくるものではありません。「やってみたら、少し戻ってきた」となるものなのです。
まとめ
「やる気がでない」のは、あなたが弱いからではありません。それは、何度もがんばって、何度も傷ついてきた心が自分を守ろうとしているサインです。学習性無気力感は、心に刻まれた「もうムダだ」という思い込みです。少しずつ書き換えていきましょう。

miho
今回も人と関わっていくうえで避けることはできない人間関係の悩みを減らすための手助けになる情報をまとめました。他の記事もありますので、あなたが今よりより生きやすくなる手助けになれば嬉しいです!X(Twitter)でお悩みの募集もしています。