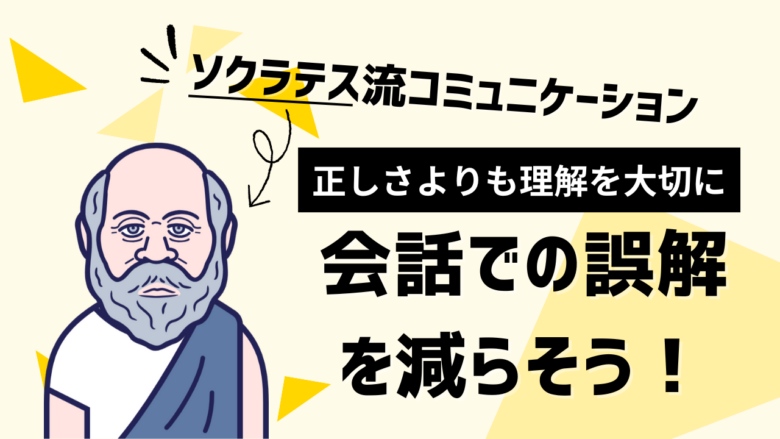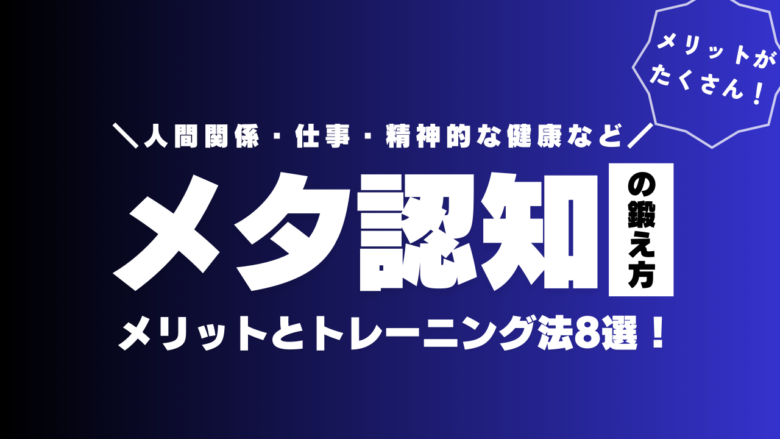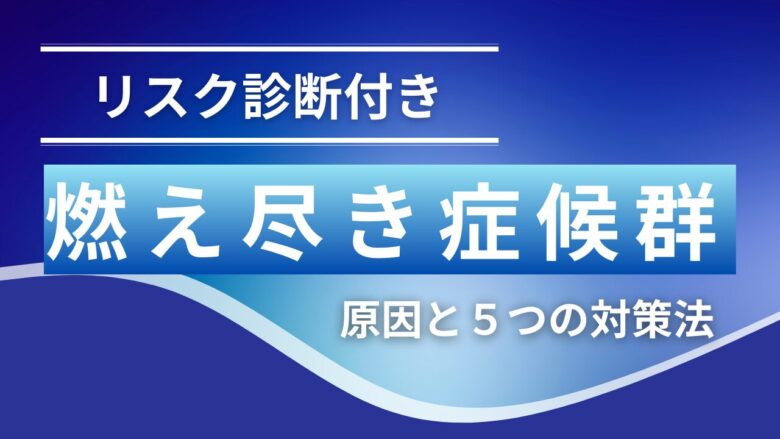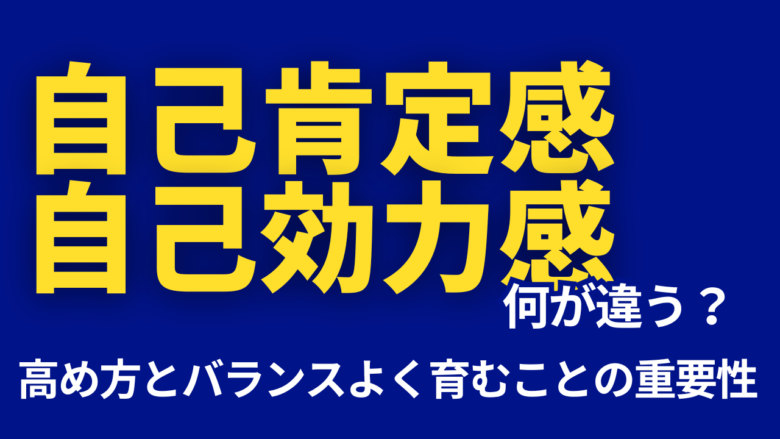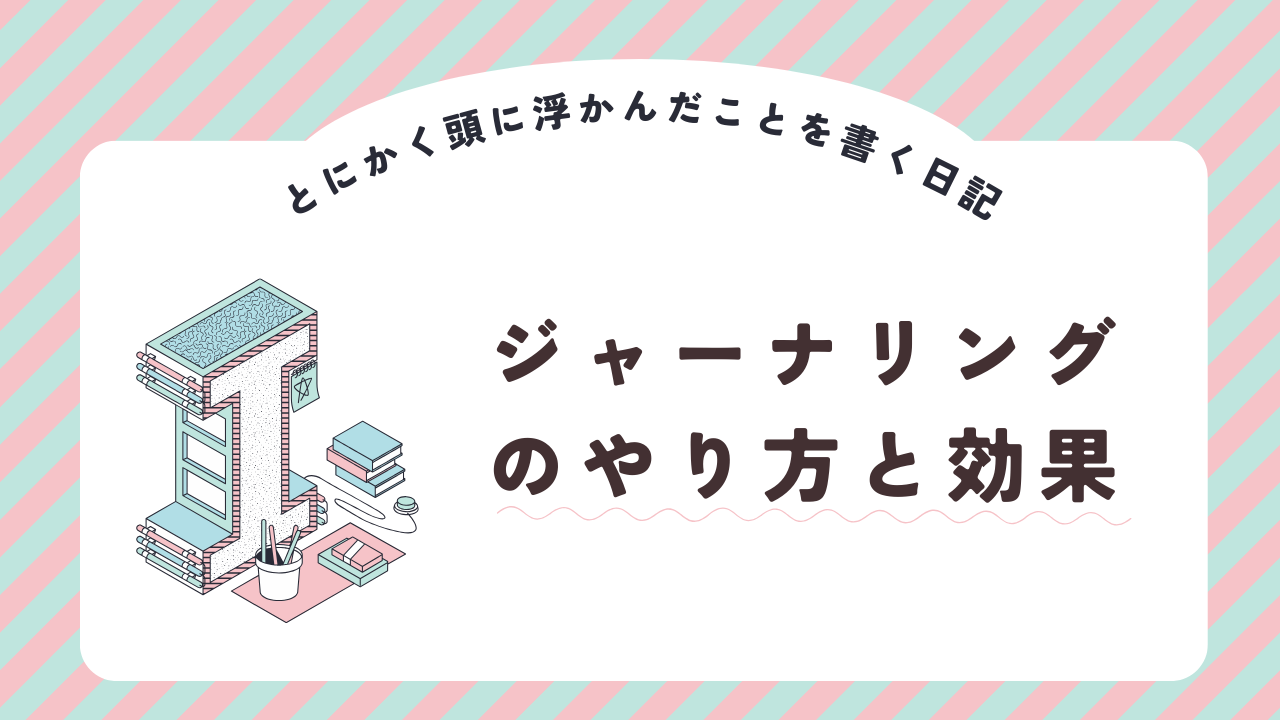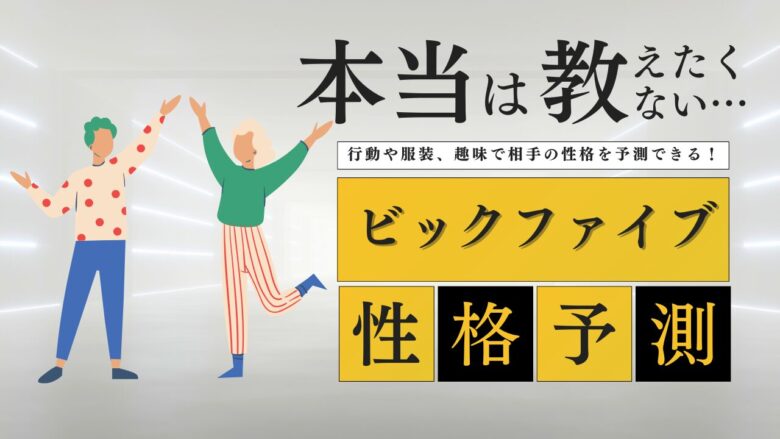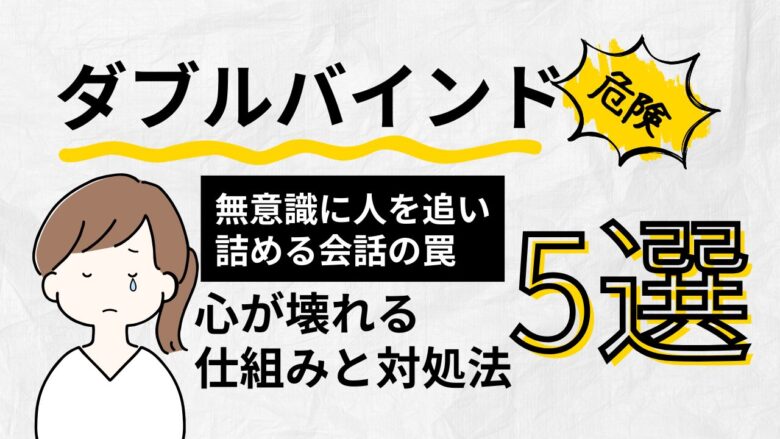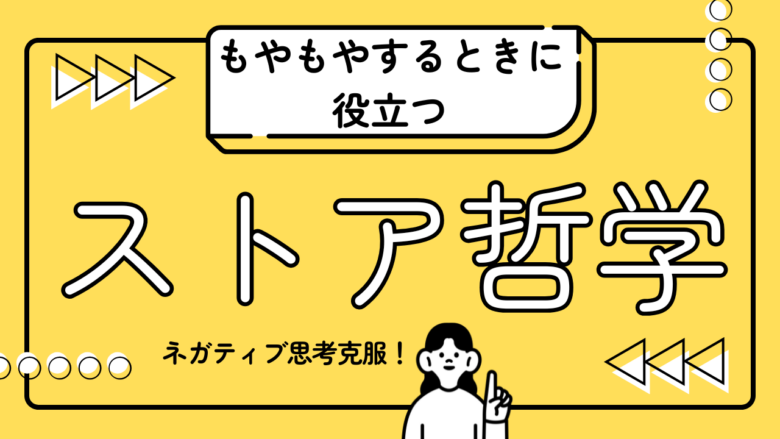「そんなつもりじゃなかった…」「なぜか相手を怒らせてしまった…」というようなすれ違いは誰もが経験したことがあるはず。このような誤解が起こるのには複雑なズレが影響しています。そうしたズレを解きほぐすためにおすすめなのがソクラテス流の問いの会話術です。この会話術を意識することで誤解やすれ違いは減り、理解と思いやりをもったコミュニケーションを取ることができるようになります。

miho
この記事は次のような人におすすめです!
- 相手の言動にすぐイライラしてしまう
- 人との会話でよく誤解されたと感じる
- 相手を論破するのではなく、深く分かり合いたいと考えている
- コミュニケーション力を高めたい
職場や学校、友達関係など、社会の中で生きている限り、人との関わりは避けられません。だからこそ、多くの人が、大なり小なり人間関係の悩みを抱えているのではないでしょうか。
国内で300万部を超えるベストセラー『嫌われる勇気』では、アドラー心理学の考え方として「すべての悩みは対人関係の悩みである」という主張が紹介されています。
このサイトでは、そんな人間関係の悩みを解決するためのヒントをまとめています。
この情報が、あなたの人生を少しでも生きやすくする手助けになれば嬉しいです!
そもそも誤解はなぜ起こる?複雑に絡む3つのズレ

①言葉の定義がずれている
たとえば「ちゃんとやって」と言われたとき、「ちゃんと」の意味は人によって異なります。
- Aさんにとっては「丁寧に仕上げること」
- Bさんにとっては「期限内に終えること」
- Cさんにとっては「ミスをゼロにすること」
同じ言葉でも、背景にある価値観や経験によって、捉え方はバラバラです。
こうした言葉のズレが誤解の入り口になります。
②暗黙の期待がある
「これくらいわかってほしい」「普通分かるでしょ?」という言わなくても分かるはずという期待は裏切られることも多いです。
自分の中では当然のことでも、相手にとっては全く意識していないことかもしれません。私たちは無意識のうちに、自分の前提を常識だと思いがちです。その前提が食い違うことで「どうしてわかってくれないの?」というすれ違いが生まれます。
③感情がフィルターになる
言葉は正しくても、感情がこもっていると受け取り方は変わります。例えば、「ちょっとまってね」と言われた時
- 急いで焦っている時には「待たせるなんてひどい」と感じる
- 余裕があり機嫌が良ければ「わかった、気にしないで」と流せる
つまり、その言葉が何を意味するかは、受け取る側の状態にも大きく影響するのです。
誤解が起こった時、私たちはつい「相手がちゃんと伝えなかったせい」「わかってくれないから」と考えてしまいがちです。
でも実際には、言葉の定義・前提・感情という3つのずれが複雑に絡んでいることがほとんどです。
だからこそ、自分も相手もズレているかもしれないという前提に立つことが、誤解をほどく第一歩なのです。
ソクラテス流コミュニケーション|問いで理解を深める
ソクラテスってどんな人?
ソクラテスは、古代ギリシャの哲学者です。プラトンの師としても知られており、紀元前5世紀のアテネで活躍しました。
実は彼は、自分では一切文字を残していないのです。思想ややり取りは、弟子プラトンなどが書き残した対話篇の中にあります。

彼が後世まで語り継がれているのは、「対話」という手段を通じて、人の考えを深める天才だったからなんです。
ソクラテスの特徴:答えずに、問い続ける
ソクラテスのコミュニケーションは、少し風変わりです。彼は「教える」のではなく、「問いかける」ことを徹底していました。
たとえば、誰かが「正義とはこういうものだ」と言った時、ソクラテスはこう問い返します。
- 「それはいつでも当てはまることなのかな?」
- 「それと反対のことが起きた場合、それは不正義なのかな?」
- 「じゃあ争うことも正義になる?」
このようにして相手の考えの前提や矛盾を優しくあぶりだしていくのです。
ソクラテス流コミュニケーションの特徴
ソクラテスの会話術は「問答法(エレンコス)」と呼ばれています。
- 問いによって相手の思考を掘り下げる
「なぜそう思うのか?」「それは他の場合にも当てはまるのか?」など - 相手に自分の矛盾に気付かせる
相手自信の言葉で、自分の理解の甘さや誤解に気付く - 結論よりも、対話のプロセスを重視する
「何が正しいか」より「どう考えるか」が大事
つまり、問いを使って相手の中身ある答えを引き出す、非常に高度で思いやりのあるコミュニケーションなのです。
なぜソクラテス流が、誤解をほどくのに役立つの?
私たちが人とぶつかるとき、つい説明する・説得する・正そうとするという方向に向きがちです。
でもそれでは相手の思考の中身を知らずに押し込むだけです。
そこで役立つのが、ソクラテスのような「問いで導く」姿勢です。
このようにソクラテス流は誤解をほどくための対話術として、現代にも応用できる知恵なのです。
日常生活で「ソクラテス流会話術」を使ってみよう
ソクラテス流コミュニケーションの特徴がどのようなものか分かっても、いきなり活用するのはなかなか難しいもの。でも実はほんの少し問い方を変えるだけで、日常のコミュニケーションでもすぐ使えます。
例①:【恋人・友人】約束の時間に遅れてきた友人にイライラ
NGな反応
「なんで遅れたの?!こっちはずっと待ってたのに!」
→怒りや責めのトーンが先立つと、相手は言い訳モードに入り、対話が成立しにくくなります。
ソクラテス流
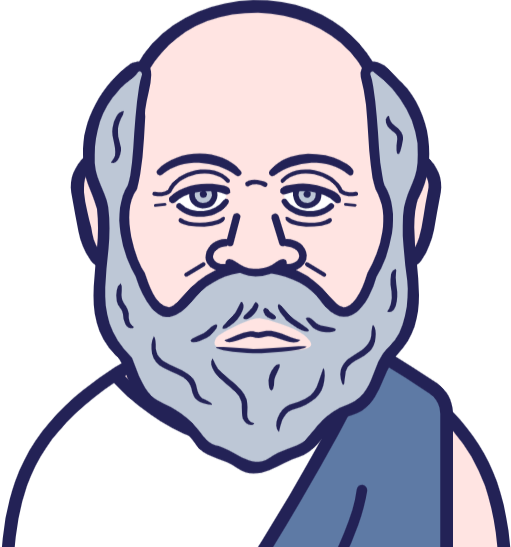
ソクラテス流
今日はどんなことがあって遅れちゃったの?
もしかして、何か予想外のことがあったの?
→相手の事情を知ろうとする姿勢を見せることで、誤解がほぐれやすくなります。
②【職場】部下に「もっとちゃんとやって」と伝えたが伝わっていない
NGな反応
「言ったよね?なんでちゃんとやらないの?」
→「ちゃんと」の定義があいまいなまま責めても、伝わらないまま。
ソクラテス流
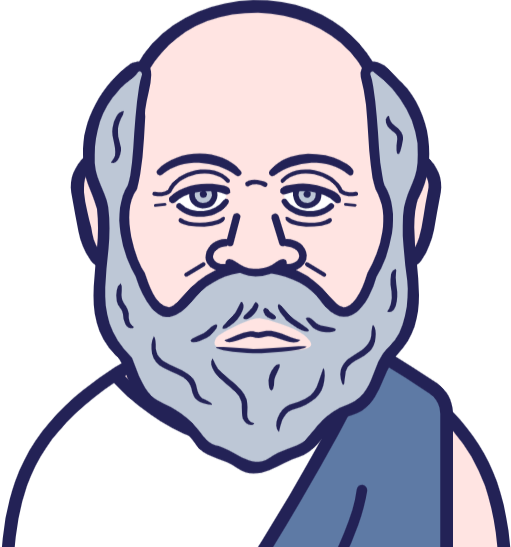
ソクラテス流
私が言う「ちゃんと」ってどういう風に伝わった?
あなたが考える「丁寧な仕事」ってどんな感じ?
→使っている言葉の定義をすり合わせることで、目指すレベルや期待が一致します。
③【家族】家事をお願いしたら不満げにされた
NGな反応
「は?何その言い方!」「やる気ないならやらなくていい!」
→感情が感情を呼び、コミュニケーションが破綻しがち
ソクラテス流
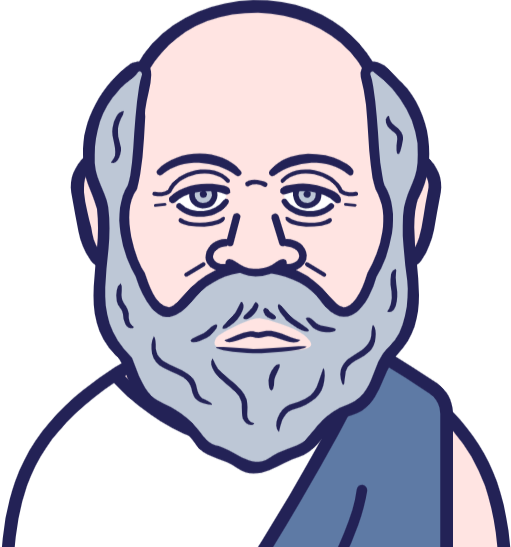
ソクラテス流
さっきの言い方、何か気になることあった?
なにか他にやることがあったのかな?
→相手の言葉の背後にある主張や感情に光を当てると、相手も自分の言い方に気付きやすくなります。
実践のポイント
1.「正す」より「探る」姿勢をもつ
多くの人は、会話の中で「相手を正そう」「分からせよう」としてしまいがち。でも、ソクラテスは相手を間違い扱いしません。
「この人はどうしてそう思うんだろう?」と探求する姿勢がベースにあります。
- なんでそんなことも知らないの?
→〇その考えにたどり着いた理由、教えてほしい!
目的は理解であって勝ち負けではありません。
2.「なぜ?」が攻撃になることも|感情のトーンに注意する
「なぜ?」と言う問いはとてもパワフルです。しかし、トーン次第で、相手を追い詰める尋問になることもあります。
- なんでそんなことしたの?(責めた口調)
→〇なんでそう思ったのか、聞いてみてもいい?
どういう背景があったの?どんな考え方があったの?と柔らかく聞く工夫が大切です。
3.答えを導くために問うのではなく、「考えさせる余白」として問う
ソクラテスの問いは、答えを押し付けるためではなく、「一緒に考えるため」にあります。たとえば、自分と違う価値観を言われた時、
- それ間違ってると思う
→〇その価値観って、どんな経験から来てるのかな?
相手が自分で考える余地を残す問いを心掛けると、強制感のない対話ができます。
4.自分の思い込みにも問いを向ける
ソクラテスの真髄は、「無知の知」→自分も分かっていないかもしれないと疑うことです。
相手に問いかけるだけでなく、自分にも問い返してみることで、すれ違いや誤解をなくすことができます。
- なぜ私はこの言葉に引っ掛かったんだろう
- 常識だと思っていたけれど、本当にそうかな?
- この怒りの正体は、期待の裏返しかもしれない
問いかけは、相手を理解するツールであると同時に、自分を知るツールでもあるのです。
5.焦らず「分かり合えない前提」から始める
すぐに分かり合おうとすると、焦りや怒りが先に立ってしまいます。でもソクラテスはそもそも人間は簡単に分かり合えないことを前提にしていたとも言えます。
- 前提が違うのかもしれない
- 相手の言葉の意味を、まだちゃんと聞いていないかも
- 答えは一つじゃない
この様なスタンスで対話すると、自然と問いも優しくなり、誤解をほどく余地が生まれてきます。
まとめ
コミュニケーションで大切なことは正しさや勝ち負けではなく、お互いに理解し合うことです。相手を深く理解するために問い、自分の思い込みや湾曲した感情に気付くために問う。このようなソクラテス流の会話術を意識することで、対話はただの言葉のやり取りの枠を超えることができます。

miho
今回も人と関わっていくうえで避けることはできない人間関係の悩みを減らすための手助けになる情報をまとめました。他の記事もありますので、あなたが今よりより生きやすくなる手助けになれば嬉しいです!X(Twitter)でお悩みの募集もしています。